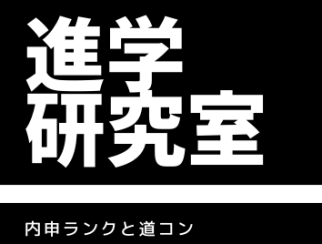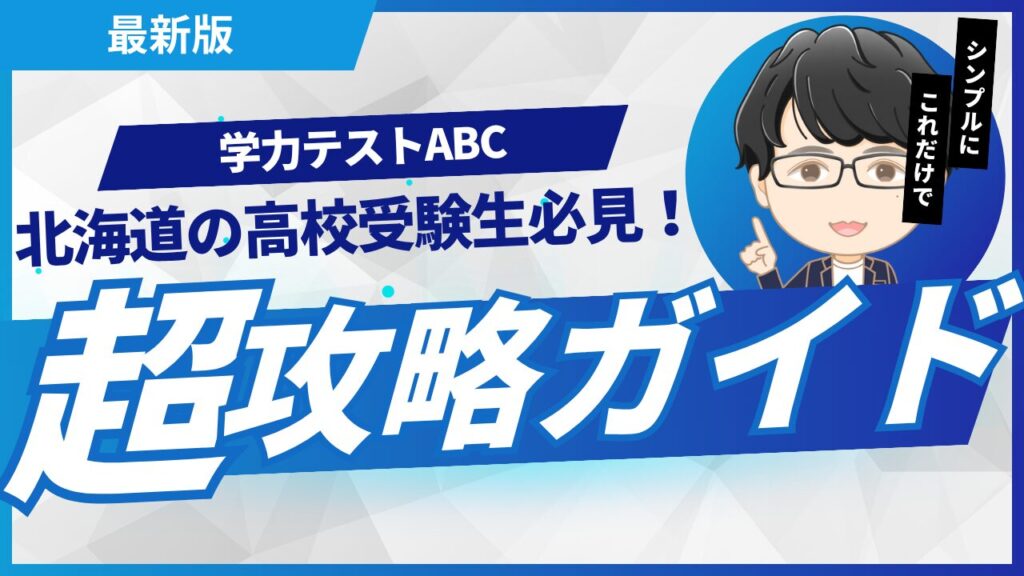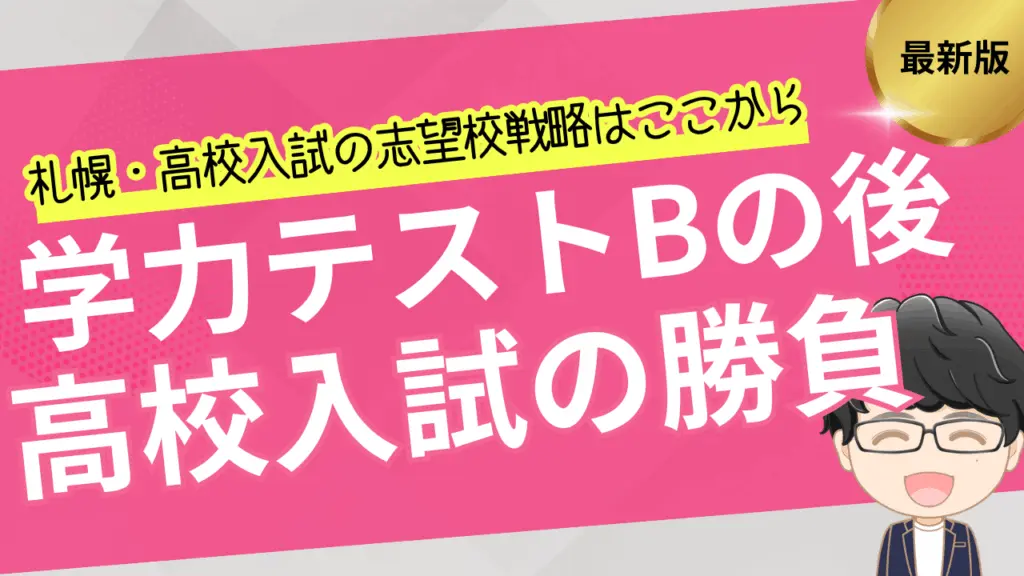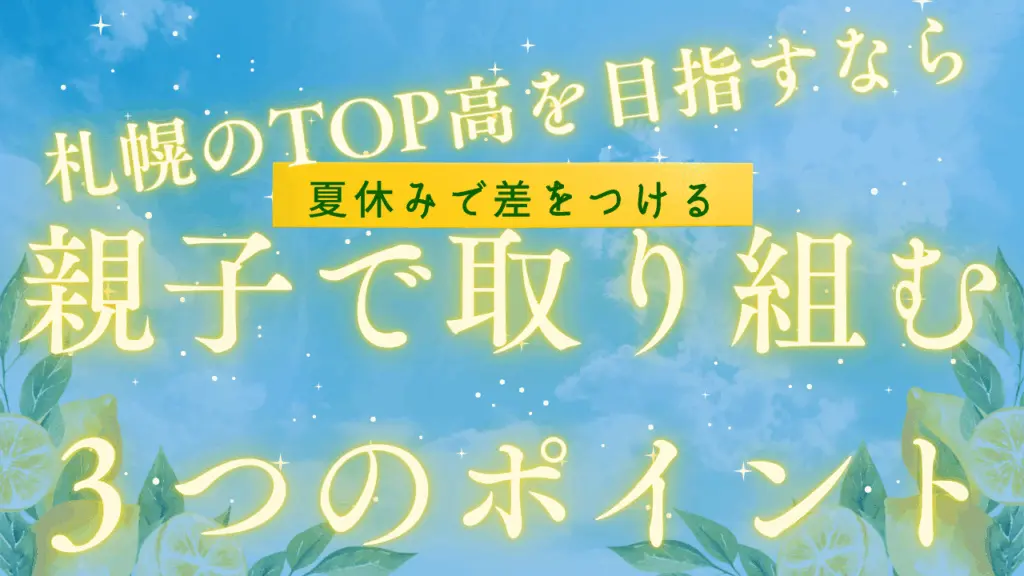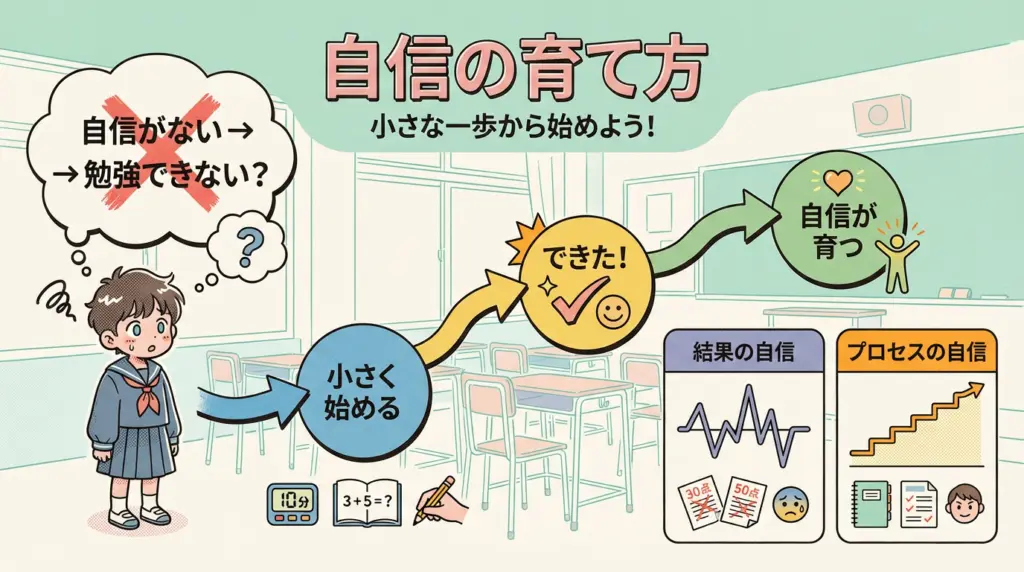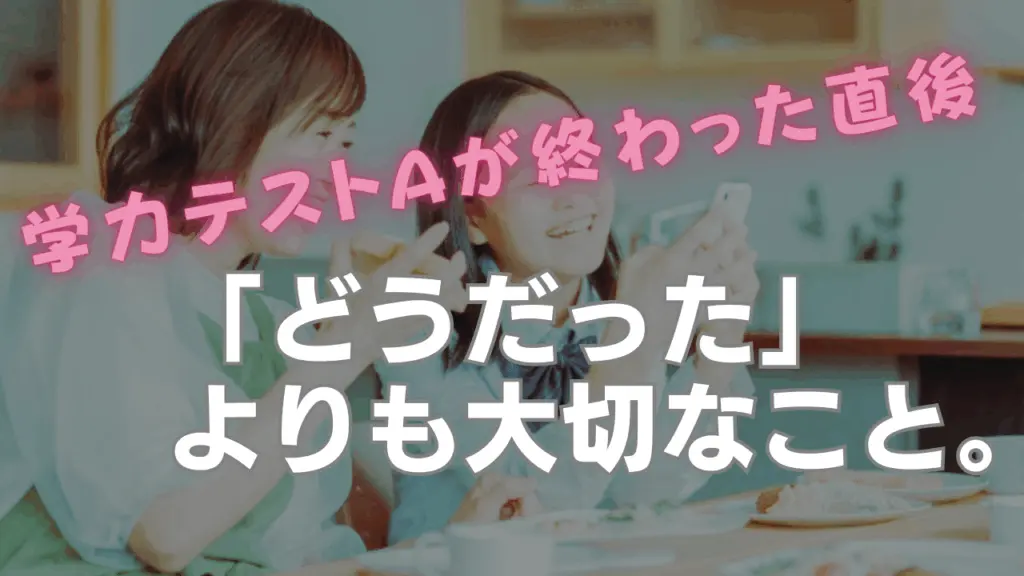
学力テストAが終わった直後の「どうだった?」よりも大切なこと 。
学力テストAが終わった日。
高校受験生の生徒さんはそれぞれの表情で教室を後にします。
達成感に満ちた笑顔を見せる子もいれば、どこか重たい空気をまとったまま帰っていく子もいます。
その姿を見送るたびに、私はいつも思います。
「この子たちの今日という日を、誰がどんなふうに迎えてくれるんだろう」と。
私は受験生を日々指導する立場として、学力を伸ばすことだけでなく、彼らの心のコンディションにも常に気を配っています。
なぜなら、結果に一喜一憂するのはもちろんのこと、その前後の「心のありよう」が、次の行動に大きく影響するからです。

「どうだった?」の問いかけが、生徒の心を閉ざしてしまうことがある
テストを終えて帰宅した生徒さんは、親からの「どうだった?」という言葉を、たいてい耳にします。
ですがこの何気ない一言が、実は本人の心にプレッシャーとして響いてしまうケースが少なくありません。
もちろん、心配してくれているのは伝わっています。
でも、その「どうだった?」が、まるで“評価の瞬間”のように聞こえてしまうのです。
特に、手応えがなかったときや、難しく感じた科目があったときは、返事をするのもつらいもの。
下手に何か答えてしまうと、あとから「だから言ったでしょ」や「もっと頑張れたんじゃない?」という言葉が返ってくるのではないかと、かまえてしまう生徒もいます。
実は、テスト後こそ“沈黙のケア”が必要なタイミング
生徒さんたちは、特に進学校(札幌でいうと東西南北)を目指す場合には、良くも悪くも「結果がすべて」という世界にいます。
それは学校や塾がそう仕向けているというよりも、受験という仕組みそのものがそうだからです。
そのなかで日々努力を重ね、ようやく迎えた学力テスト。
終わった直後の彼らには、「できた・できなかった」に加えて、「言いたい・言えない」の葛藤も生まれています。

そのため、テスト後の家庭で必要なのは「問い詰めること」ではなく、そっと寄り添う時間です。
むしろ、言葉はなくていい。
「お疲れさま」の気持ちをこめて、本人の好きな夕飯を出してあげる。
それだけで、生徒さんは「ああ、見ててくれてるんだ」と感じ、心がほどけていきます。
できなかったとき、いちばん悩んでいるのは本人です
指導の現場にいると、結果が思うように出なかったときの生徒さんの葛藤を、日々目の当たりにします。
中には、涙をこらえながら「次こそは」と言葉にする子もいます。
何も言わずに答案を鞄の奥にしまい込む子もいます。
そんなとき、本人の中ではすでに「自己分析」が始まっているんです。
「何が足りなかったか」「どうすればよかったのか」――それを考えている最中に、外から正論をぶつけられると、気持ちの整理ができなくなってしまう。
結果、意欲が削がれたり、自己肯定感が下がってしまうこともあります。
だからこそ、お願いしたいのです。
テストの点数や内容よりも、まずはその子の「がんばった事実」を認めてあげてほしい。
それはきっと、次への一歩を踏み出す力になります。
保護者の「行動」が、何よりの応援になる
私が保護者の方々にいつもお伝えしているのは、「言葉で応援しようとしないでください」ということです。
その代わりに、「行動で気持ちを示してください」。

例えば──
・好きなメニューを用意して、無言で食卓に出す
・「お疲れさま」のメモをそっと置いておく
・いつもより少し早く帰ってきて、リラックスできる時間を作ってあげる
これらはすべて、子どもにとって「ちゃんと見てくれてる」と感じられる行動です。
反応を無理に引き出そうとするよりも、こうした“静かな応援”の方が、子どもの心にはずっと深く届くことがあります。
まとめ:見守る勇気が、受験生の背中を押す
親だからこそ、気になるのは当然です。
でも、大事なテストの後こそ「ぐっとこらえる」ことは、愛情のかたちのひとつだと思っています。
受験生にとって、家は安心できる場所であってほしい。
結果に関係なく「自分でいられる場所」であってほしい。
だから、どうか「問いかける勇気」ではなく「見守る勇気」を選んでほしい。
先生として、心からそう願っています。