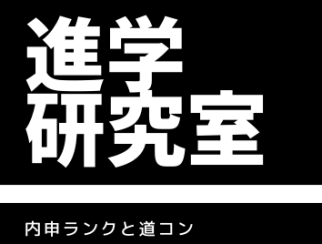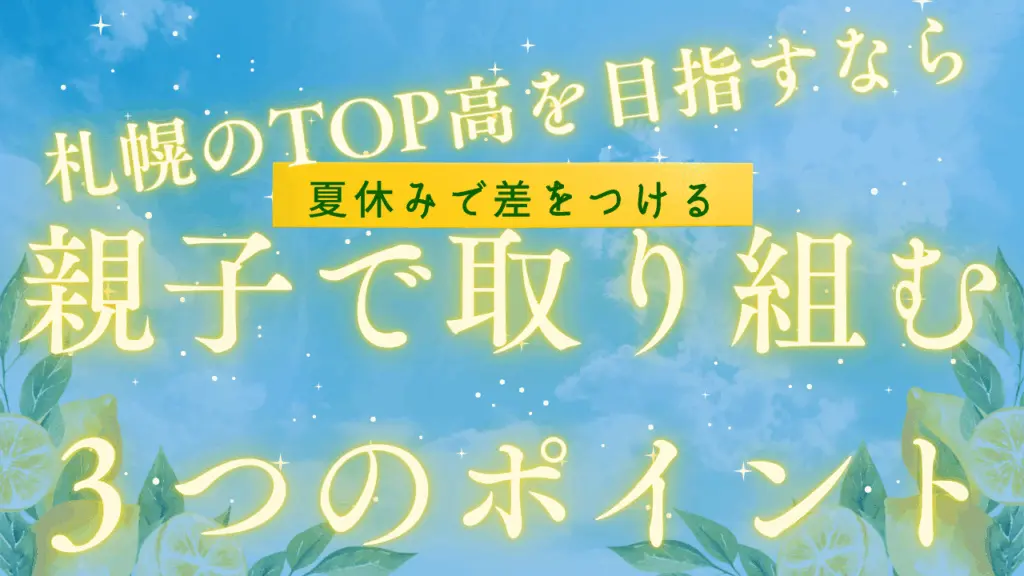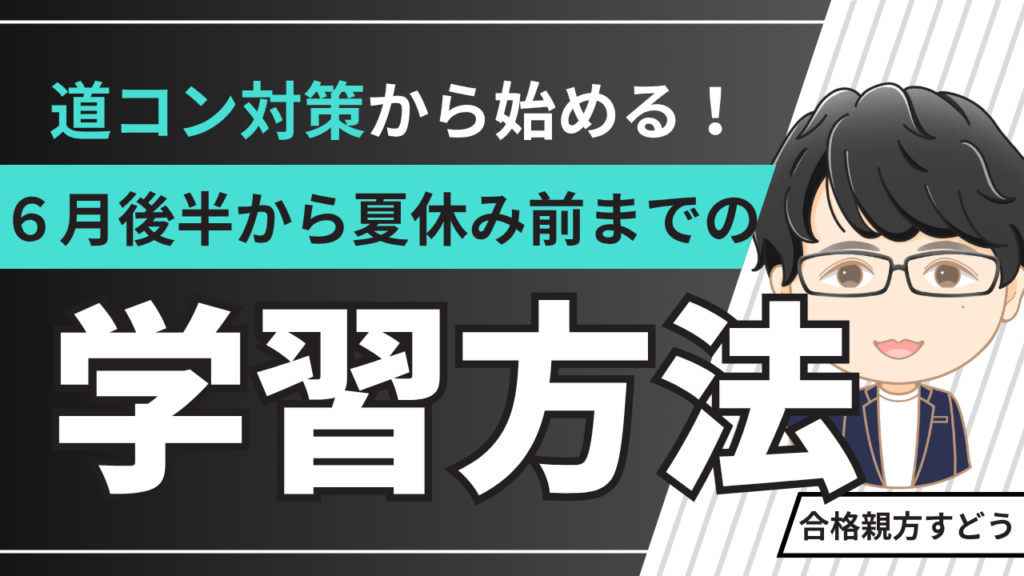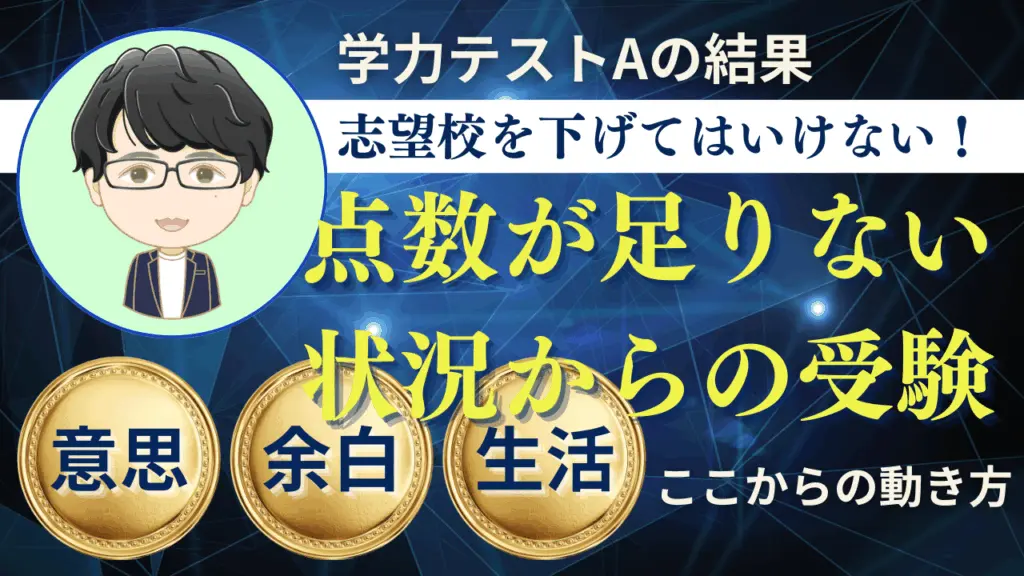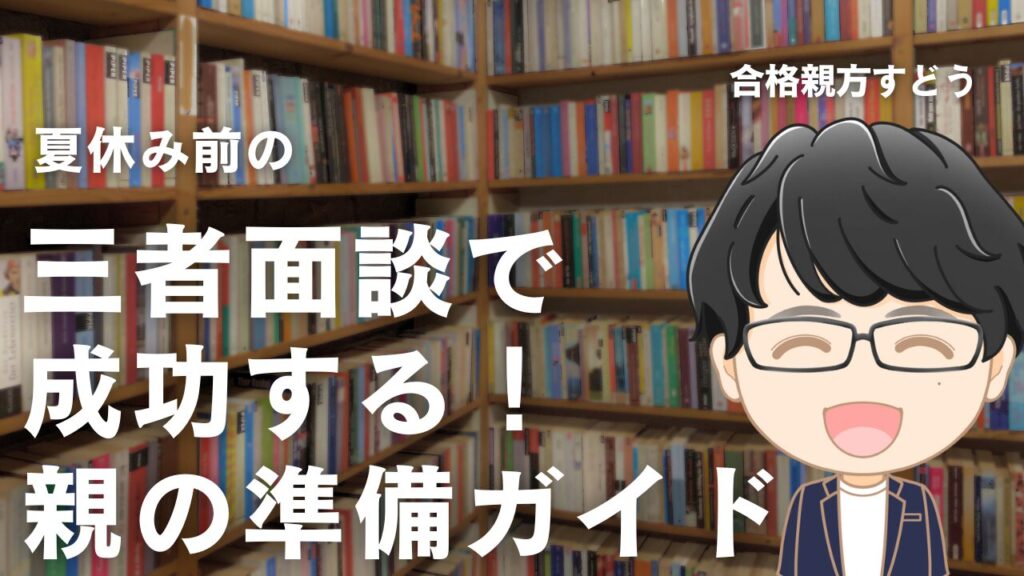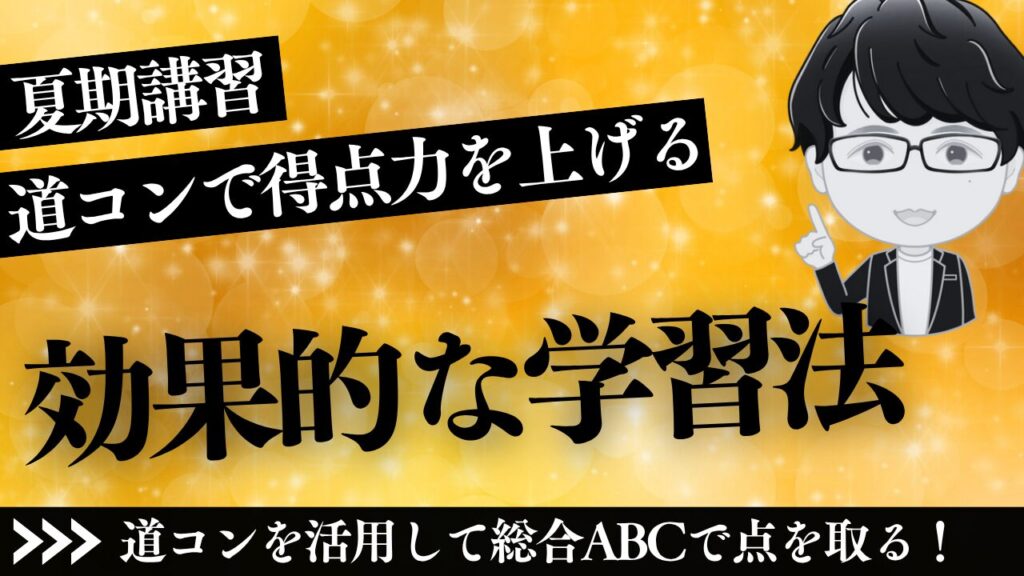【総合ABC VS 内申ランク】受験生はどちらを優先させるべきか
はじめに:総合ABCとは何か?なぜ重要なのか?
北海道の公立高校受験を目指す中学3年生にとって、総合ABC(学力テストABC)は志望校決定を左右する最重要テストです。
9月から11月にかけて実施されるこの3回のテストは、単なる実力テストではありません。
「中学校で行われる」入試本番に近い形式で行われる学力テストです。
中学校で行われる意味を深く考えていただくと、北海道の高校受験生にとってどれだけ重要なものなのかを理解していただけると思います。
学習塾などで行われる模擬試験と同じように見る受験生・保護者は少なくありません。
しかし、北海道独自のものではありますが、中学校の進路指導で志望校決定の重要な資料となることは忘れてはいけません。
また、高校入試本番への実力養成の機会でもあります。
模擬試験的な要素もあるのは事実です。
3回の学力テストの範囲をしっかりと学ぶことで、中学校で学んできたこと全体を復習することができます。その上、出題される範囲を総合ABC(学力テストABC)に合わせて取り組んでいくことで、志望校合格に向けての受験勉強を進めていくことができます。

総合ABCの基本情報
実施時期:9月(総合A)、10月(総合B)、11月(総合C)
教科:国語・社会・数学・理科・英語(各100点、合計500点)
試験時間:各教科50分
STEP 1:総合ABCの出題傾向を完全理解する
全体的な傾向
総合ABCは中学3年間の学習内容を幅広くカバーしていますが、テストごとに出題範囲の比重が変化します。
ABC別出題範囲の変化
総合A(9月):中学1・2年生の内容が中心、一部中3範囲
総合B(10月):中学1・2年生中心+中3範囲が追加
総合C(11月):中3範囲が約3割に増加、入試レベルに接近
11月のはじめに定期テストがある中学校が札幌には多くあります。
定期テストの日程と出題範囲を確認ながら準備をする必要があります。
特に、内申ランクが上がりそうな場合には、定期テスト対策にも力をいれなくてはいけません。
9月で前期の成績が出たら、10月以降の入試戦略については相談と確認をしておくことをオススメします。

受験生本人の気持ち(本音)と学習塾・家庭教師との考えとのギャップ、保護者の本音が異なっていると、合格するための学習に取り組むことができずに、せっかく成績が伸びてきていも失速するケースは少なくありません。
STEP 2:効果的な学習戦略を立てる
月別学習戦略
9月(総合A対策)
学校の授業の予習・復習と総合A対策の時間を確保
苦手科目・単元の特定と夏期講習などからの復習の継続
解答スキルの確認と、計算力・英単語などの強化
ほどんどの受験生は、夏(夏期講習)での学習で1・2年の基本知識には触っている状況だと思います。継続して1・2年生の学習と3年生の学習を並行してできるかどうかが差になります。
1・2年の学習と並行して、中3の学校の授業の予習・復習を行える学習習慣(生活習慣)を整えていくのが2学期始まってすぐの最大の課題になります。
10月(総合B対策)
総合Aの結果分析と解答の手順などの確認
中学1・2年生の入試基礎レベルでの演習
社会・理科の重要語句のIN PUT
「間違えた理由を探る→解き直し→類題演習」のサイクル実践
中3前期の成績が出て、ほぼ内申ランクが決まった時期です。
受験戦略の方針は固めて行かないといけない時期です。
内申ランクを上げるために、成績をいくつ上げなくてはいけないのか。
また、逆に成績がいくつ下がったら内申ランクが下がってしまうのか。
内申点としてはわずかな差であっても、北海道の高校入試では点数ではなく内申ランクが重要になります。
たった内申点では1点であっても、ランクが下であれば志望校を変えなくてはいけないくらいです。
総合Aの結果で、公立高校入試本番で必要な点数に対して、どのくらい差(点数・偏差値)があるのかもある程度見えてくる(わかってくる)時期でもあります。
志望校の確認、入試戦略の確認をこの時期にしっかりと行いましょう。
札幌市内の中学校では11月のはじめころに定期テストが行われることが多いですし、総合Cも同じような時期に行われます。
志望校の合格に必要な内申ランク・偏差値に余裕がないのであれば、この時期の学習はなんとなく進めるでは不安を感じます。
学習塾・家庭教師と学習の方向性を保護者の方は確認しておくべきです。
セカンドオピニオンとして、利用している学習塾・家庭教師ではない入試の専門家の客観的な意見・アドバイスをもらうのもこの時点では役に立ちます。
場合によっては、学習塾・家庭教師などの環境を変えることも検討するべきです。
これまでの期間で結果が出ていないのであれば、これから入試までに結果を出すことのリスクも大きいのですから、前向きにリスクを取る決断するのであればこの時期が最後になるかと思います。
志望校決定までのカウントダウンがはじまっていますから時間はありません。
この時期に環境を変えて成功した受験生を何人も見てきています。
本当のラストチャンスになるかもしれませんので、入試への方向性・環境作りを保護者は行います。
11月(総合C対策)
定期テストの日程・範囲を確認しながらの計画作成
「中3範囲」の総合Cと定期テスト対策をバランスよく行う
10月に確認した入試戦略に沿って進めていくことが前提となります。
1〜3教科上げることで内申ランクが上がる場合、定期テストを優先させるべきだと個人的には考えています。
私立高校の受験校を決める時期でもありますので、しっかりと入学した場合のことを考えて学校説明会・相談会に参加してください。
STEP 3:過去問を最大限活用する
過去問入手方法
中学校:まずは学校の先生に相談してみましょう。
教科によっては授業で扱ってくれたりするケースもあります。
中3の学習内容(教科書)の進み具合で余裕がないと難しいかも知れせん。
北海道学力コンクール(道コン):総合ABC対策模試の活用
出題範囲が同じで、問題のレベル感がかなり近いのでオススメです。
北海道学力コンクール(道コン)WEBから申し込みが可能です。
解説におまけでついてくる問題からも出題されるのでやり尽くしてください。
学習塾:過去問入手と解説指導
学習塾によって力の入れ方は違いますので、心配な場合は事前に相談・確認をしておくと安心ですね。
市販教材:「高校入試 落とせない入試問題 5教科セット」と「道コンセレクション」
本屋さんで買えるテキストとしてはこの2つをオススメします。
学習塾や家庭教師を利用している場合は、そちらの先生と相談してください。
自分に合った学習量があるかと思いますし、すでに学習しているものを復習することが良い場合もあります。

10月に確認した入試戦略に沿った学習を進めましょう。
学習内容について不安を感じたら、細かく確認をすることも大切です。
学習塾・家庭教師とは気軽に相談をしていきます。
11月に定期テストがある場合はその結果も考慮して、総合ABCの結果と予想できる内申ランクで受験校を決めていきます。
もちろん、総合ABCの点数の推移にプラスして、道コンの10月・11月の結果を見て決めていきます。
STEP 4:総合ABC結果を志望校決定に活用する
11月の後半になってから行うことになるかと思います。
総合ABCの結果と定期テストの結果を見ていきましょう。
道コンを受験している場合はそれも使っていきます。
結果活用の心構え
一喜一憂しない:結果は現状把握のためのデータ
客観的分析:感情ではなく数値に基づく判断
建設的活用:弱点発見と改善計画立案のツールとして使用
この作業をするときに、保護者の方が感情的になるケースがあります。
気持ち的にはすごく理解できるのですが、この状況で感情的になっても、成績や点数の向上にはつながりにくいかもしれません。
受験校の最終決定にもつながる時期なので、セカンドオピニオンとして、利用している学習塾・家庭教師以外の入試の専門家の客観的な意見・アドバイスをもらうのもこの時点でもプラスになると思います。
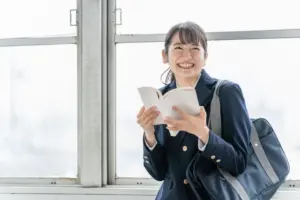
月別学習学習戦略のところでも書かせていただきましたが、10月の段階でしっかりと親子でこれからについて相談と確認をしていると、ここでの現状確認は気持ち的にも楽だと思います。
重要な自己分析ポイント
総合ABCでは、全体得点を以下に分けて分析することが重要です:
中学1・2年生範囲の得点率
中学3年生範囲の得点率
危険信号の見極め
ここでは範囲と書きましたが、単元として細かくみることが多いです。
例としてあげるならば・・・
社会の教科全体で考えるのではなく、分けてみていくと、
社会
=地理
+歴史
+公民
さらに、
社会
=日本地理+世界地理
+室町時代まで+戦国時代+明治維新前後+近代
+日本国憲法+経済
ざっくり分けてみて、どこが点数が取れていて、どこが取れていないかをみていくとよいです。
全く得点できていない分野は、特に注意が必要になります。
12月中学校の三者面談での活用法
志望校決定の最終段階:志望校と現実のギャップを認識
具体的改善計画:残り期間での学習戦略立案
保護者・教師との連携:客観的データに基づく進路報告
12月の前半で受験校を決定し、三者面談に臨むことになるかと思います。
三者面談の場では実際の相談ではなく、主に受験校を報告するような馬になることが多いです。

内申ランクが1〜2個で上下する場合は、それについて相談するような形になります。
内申ランクが下がると志望校を変更しなくていけなくなるようなケースは、どのようにすると良いのかのアドバイスとヒントを学校の先生から直接もらえるようにしましょう。
最後に:総合ABCは通過点、目標は志望校合格
総合ABCは重要ですが、あくまで高校入試合格への通過点です。
結果に一喜一憂することなく、自身の学力向上と志望校合格という最終目標に向けて、着実に歩みを進めていきましょう。
「わからなかった」からこそ、新しい発見が待っている – この前向きな姿勢こそが、総合ABC、そして高校入試成功への鍵となります。
この記事が北海道の中学3年生のみなさんの総合ABC対策や高校受験成功の一助となれば幸いです。戦略的な学習と継続的な努力で、目標達成を心から願っております。もし、入試についてのご相談などがありましたら気軽に相談フォームからお願いします。