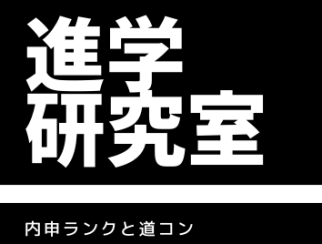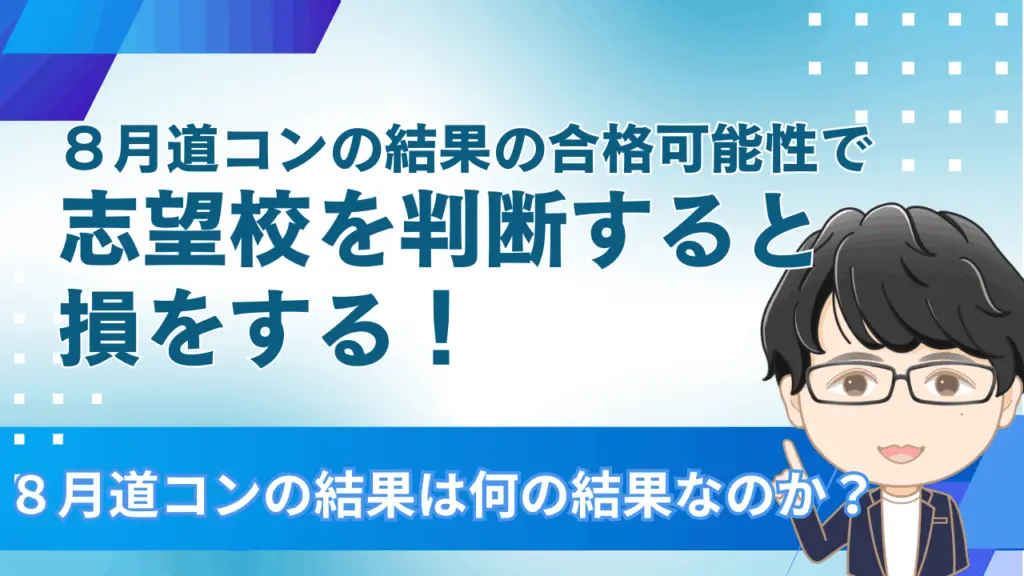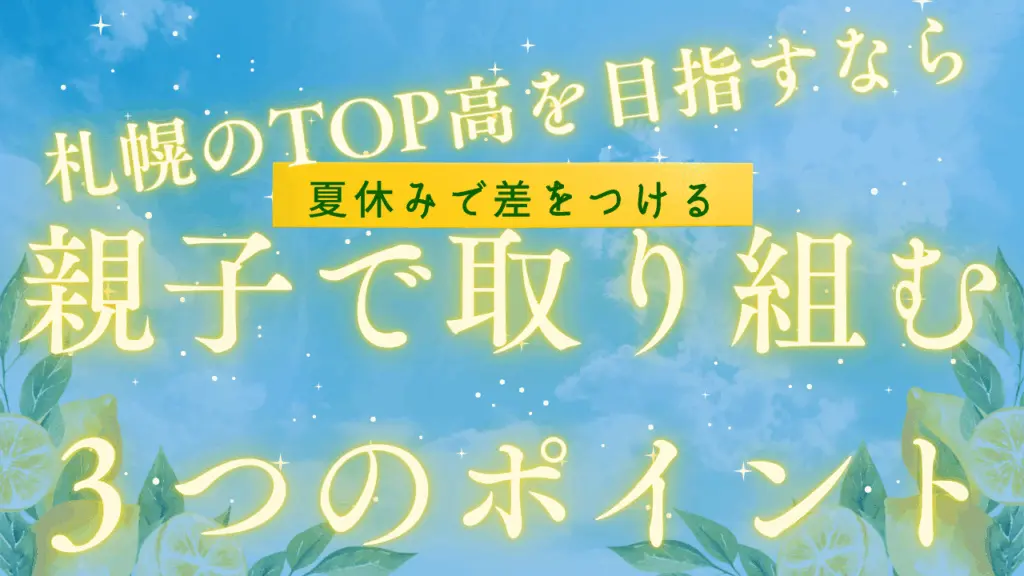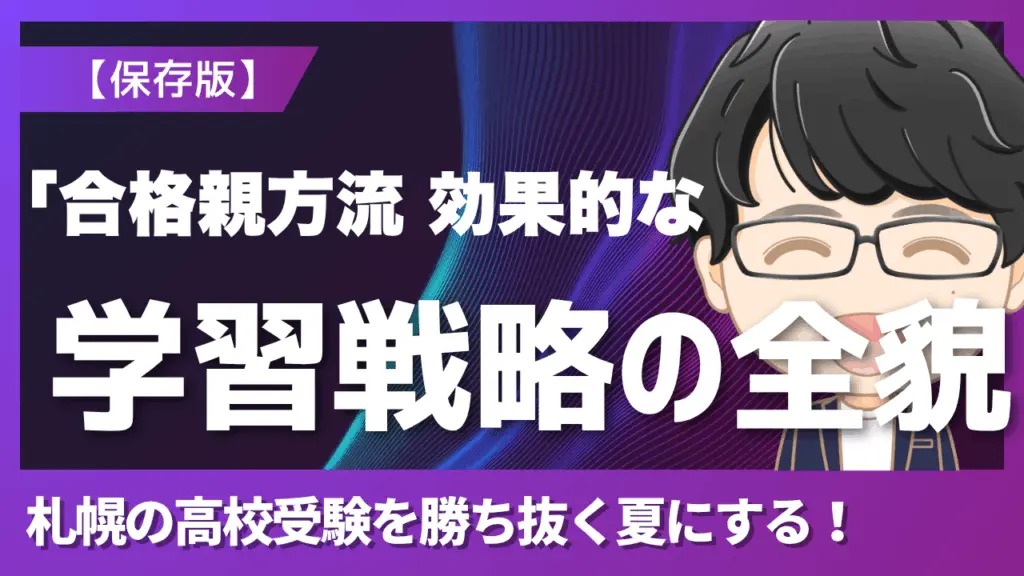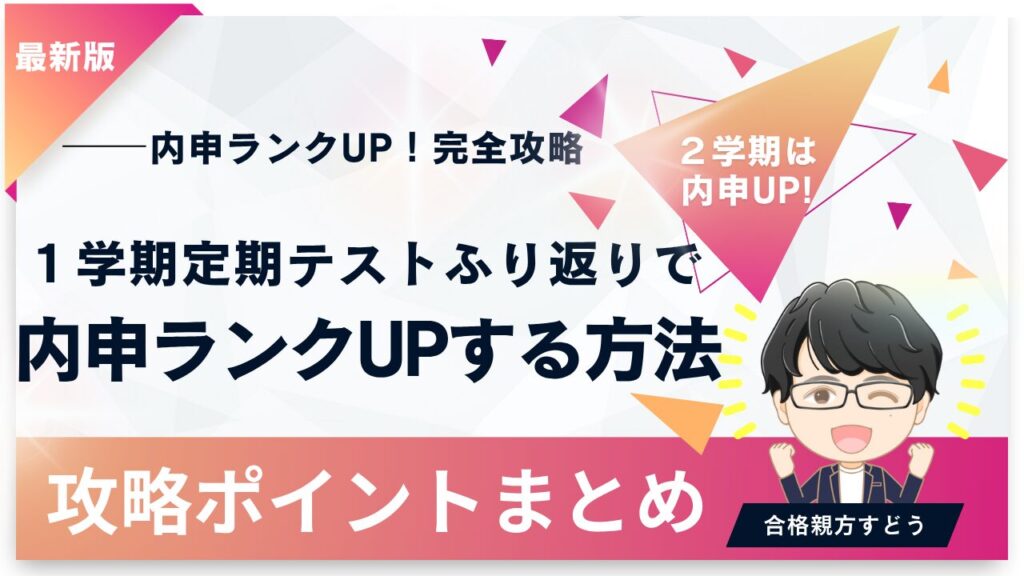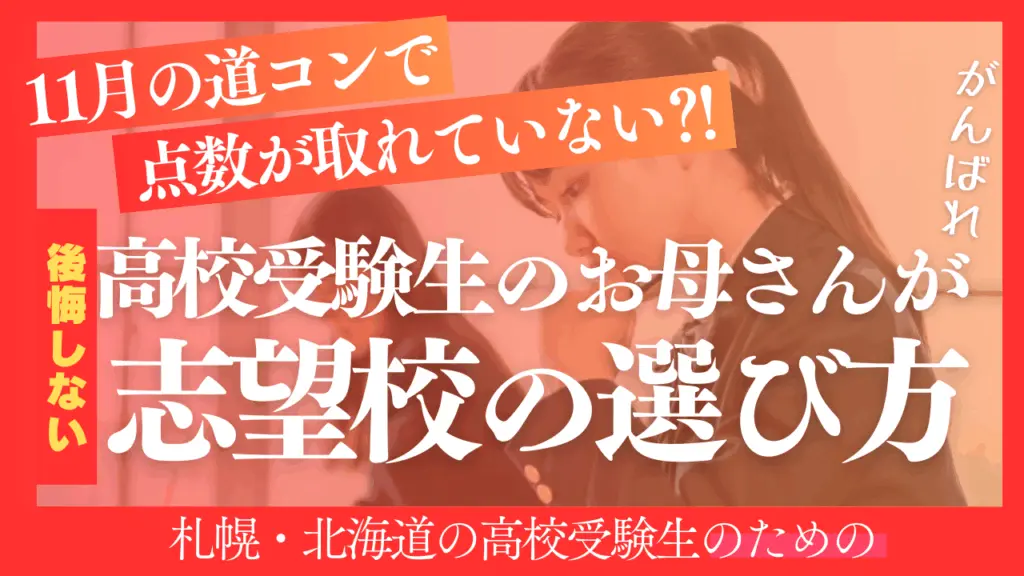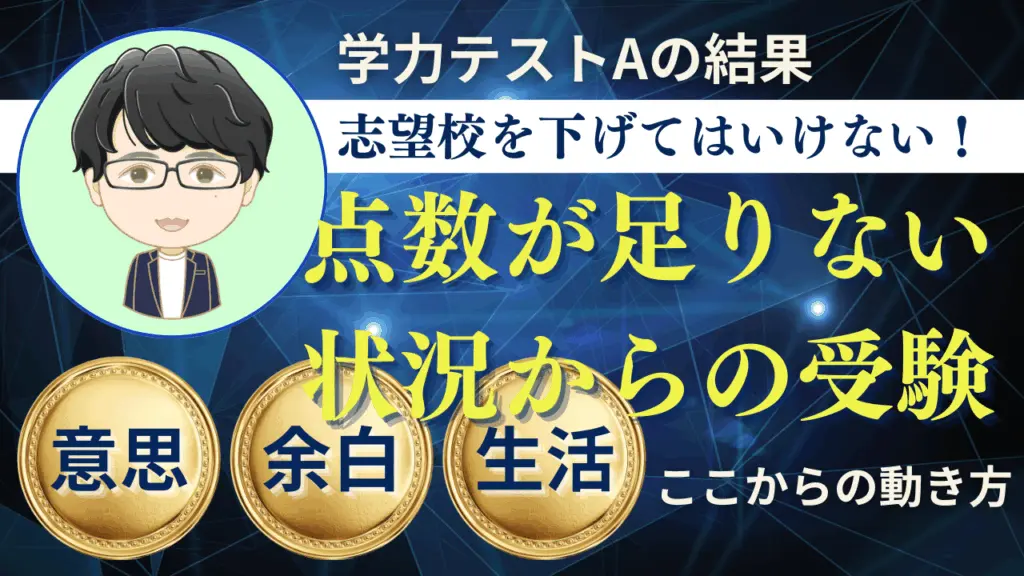
学力テストAで志望校を下げてはいけない!
——点数が足りない状況からの受験「ここからの動き方」
学力テストAでは「現在地」がわかっただけ
高校受験生の中3にとって学力テストAは、これまでの定期テストとは重みが違います。
はじめて「高校受験が始まった」と体で感じる瞬間。
結果を見て「志望校、下げたほうが安全かな」と揺れる気持ち、痛いほどわかります。けれど、結論を急ぐのはもったいない。毎年多くの受験生を見てきましたが、学力テストAは“合否の宣告”ではなく“現在地の座標”。
ここからの伸び方次第で景色は大きく変わります。

結果を読み解いていくことが大切
まずお伝えしたいのは、志望校の判断軸を「偏差値だけ」に置かないこと。
志望校は、あなたが本当に行きたい場所かどうか——その熱量が学習の推進力になります。
もちろん、現実的な見取り図も必要ですが、数字が先に心を小さくしてしまうと、努力の質が落ち、かえって離れてしまう。だからこそ、最初の仕事は「結果の読み解き」と「伸びる設計」です。
結果の読み解きでは、点数や判定を“分解”します。
教科別・大問別・設問形式別に弱点を特定し、ケアレスミスと実力不足を分ける。
例えば数学は「計算・関数・図形・証明」、英語は「語彙・文法・長文・英作文」、国語は「漢字・語彙・説明的文章・文学的文章・古典」といった具合に棚卸しをし、次回テストまでに“どこで何点取り返すか”を明文化します。
ここでの目標は「次の模試で+○点」ではなく「長文の設問2と3で取りこぼしゼロ」など、行動に直結する指標にすることです。

伸びる設計は、30日逆算→週次PDCA→日々のルーティンの三層構造が有効です。
30日で克服したいユニットを決め、週のはじめに範囲と量を確定、週末に小テストで検証。
日々は「朝15分の英単語アウトプット」「帰宅後30分の数学“解き直しだけ”」「寝る前10分の理社暗記ドリル」のように、短い固定メニューを積み重ねます。
特に“解き直しノート(間違えノート)”は最強の武器。間違えた問題の原因・正しい考え方・次に同系を落とさない一言ルールを書き、定着させましょう。過去の自分に勝つことが、最短の伸びにつながります。
今から本当に行きたい志望校を目指すために
志望校を「上げる・維持・下げる」を検討する基準は三つ。
①意思:その学校に通う自分を想像してワクワクするか。
②余白:入試本番までの期間×教科別の伸び代。現実的に埋められるギャップかを見積もれるか。
③生活設計:睡眠・スマホ・部活・家庭学習時間のルールを現実的に運用できるか。

この三つが整うなら、私は「挑戦」を推します。
逆に①が薄い場合は、志望校を見直すことをオススメします。
保護者とのコミュニケーションも大切です。
「志望校を下げる=安全」ではありません。
目標が下がることで努力の炎まで弱まるケースもあります。ご家庭では、結果の善し悪しより「次の一手」を一緒に言語化してください。「今回は計算ミスが5問。毎日10分の計算ルーティンで2週間後にミス半減を目指す」といった、具体の約束が子どもの安心と行動を生みますが、押し付けるような形は望ましくないので注意が必要です。
今から「間に合わせる」
よくある不安にも答えます。「今からで間に合いますか?」——間に合うように設計すれば間に合います。第一志望に向けた学習を主軸に据えるのがコツ。安全校対策だけを先に固めると、第一志望に必要な思考量・スキルが不足しがちです。

志望校を下げるという提案は、ときに親切心から出ます。
ただしそれは、「ここからあなたは伸びない」という前提で語られがち。学習塾の先生からその言葉が出るということは、受験生をこれから伸ばすことが難しいと宣言するようなものではないでしょうか。
私は、ここから伸びる設計を一緒につくる側です。学力テストAは、あなたの可能性へのスタート合図です。迷ったときこそ、行きたい学校への気持ちをエンジンに、具体的な一手から始めましょう。今日の15分が、判定の数字を動かします。